臨床精神医学第49巻第2号
依存・嗜癖とその考え方の変化
電子書籍のみ
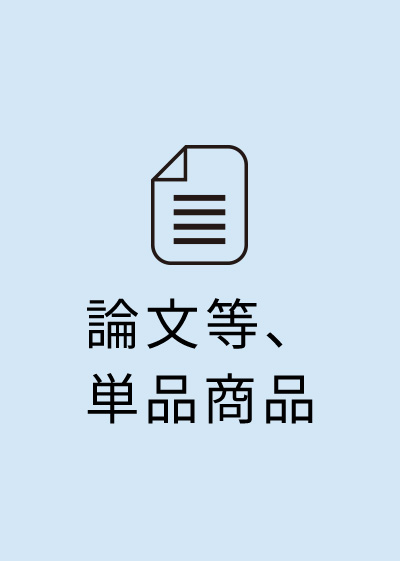
- 宮田 久嗣(東京慈恵会医科大学)
- 発行日:2020年02月28日
- 〈抄録〉
依存(dependence)と嗜癖(addiction)ほど紆余曲折を経てきた精神科用語は珍しいかもしれない。その背景には,さまざまな種類の物質が乱用されてきたこと,加えて最近は,物質だけではなく,ギャンブルやゲームなどの行動も共通の疾病カテゴリーで考えられるようになったことなどが関係している。依存に関しては,WHOの定義にあるように「生体と物質の相互作用の結果生じた生体の特定の状態であり,物質への渇望が中心症状であるが,断薬や減薬による離脱症状の苦痛は渇望を増強させる」と説明される。したがって,依存は物質に対して用いられる用語であり,ギャンブルやゲームのような行動には使用できない。一方,嗜癖に関しては国際的に明確な定義はないが,「何かにのめりこんでコントロールを失っている状態」と解釈される。したがって,嗜癖はギャンブルやゲームのような行動に対して用いることができる。その意味では,物質使用も嗜癖行動と考えることができる。物質使用の結果,渇望(精神依存)や離脱症状(身体依存)が生じた場合を物質依存と呼ぶことになる。したがって,嗜癖と依存の関係を一言でいうならば,嗜癖の中で,物質使用によって生じた特定の状態が依存である。本稿では,依存や嗜癖の概念の変遷をたどりながら,その適切な使い方を考えてみたい。
詳細
Transition of concept of dependence and addiction
宮田 久嗣
東京慈恵会医科大学精神医学講座