臨床精神医学第51巻第5号
西洋の歴史にみる脳神経内科と精神科との関係
電子書籍のみ
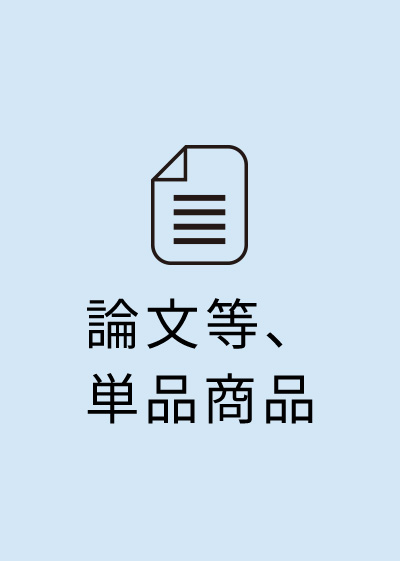
- 柴山 秀博(亀田メディカルセンター)
- 発行日:2022年05月28日
- 〈抄録〉
理解しがたい人,普通ではない人をなんとかしようという過程で西洋では19世紀初めに精神医学が形成され,その中から剖検等により中枢神経系に病変の確認される病態がおよそ50年後にシャルコーらによって確立された脳神経内科の管理に移行していった。確認可能な病変の捉え方によってヒステリーはしばらくの間脳神経内科の疾患とされた。脳神経内科が脳の機能局在や神経細胞間の線維連絡を明らかにしたのに対し,精神科は精神分析をはじめ精神症状の説明に有効な理論を作れず,反精神医学の影響も受けて1980年代からは生物学的なアプローチへと転換していった。現在ではさまざまな方法で脳の状態が可視化され脳神経内科と精神科の区別が曖昧化している。画像を前に脳神経内科では一定の経過をたどる疾患を持った患者を見ているという認識があるが,精神科ではDSMが疾患という言葉を排除しているように脳の状態のみを見ているのではないかと危惧される。
詳細
Interrelation between neurology and psychiatry viewed from history of the Occident
柴山 秀博
亀田メディカルセンター脳神経内科