臨床精神医学第52巻第4号
精神病臨床的ハイリスク群の脳画像研究による病態解明と臨床応用
電子書籍のみ
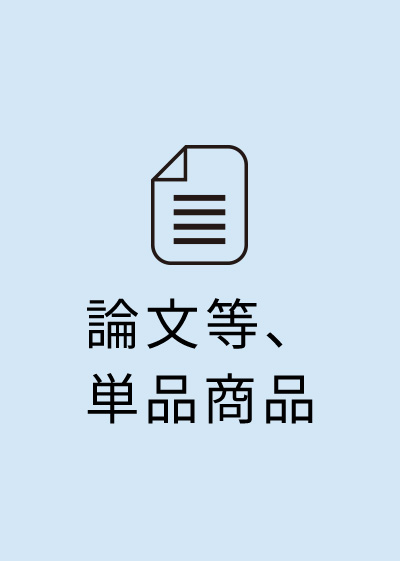
- 小池 進介(東京大学)
- 発行日:2023年04月28日
- 〈抄録〉
磁気共鳴画像(MRI)が精神疾患の臨床研究に応用されて30年余りが経ち,精神疾患の脳病態が可視化されてきたが,こうした成果から診断バイオマーカーや創薬に結びついた臨床応用はない。この原因として,機種やプロトコルの違いによる差(機種間差),疾患特異性・共通性の問題,発達や加齢変化を十分に除外できていない等があげられる。特に多施設MRI研究において機種間差の問題は大きい。これらの限界点を超えるべく,日本医療研究開発機構(AMED)国際脳プログラムをはじめとして,分野横断の多施設MRI共同研究体制が構築されている。こうした脳MRI研究の進展によって,検証的研究,疾患横断理解,基礎研究との融合,機械学習等による臨床応用の実現にシフトしつつある。精神病ハイリスク研究においても,多施設による疾患横断研究への組み込み,思春期の定常脳発達の中での位置づけが今後の課題であり,さらには臨床研究の限界を超えたコホート研究との融合が求められる。
詳細
Brain magnetic resonance imaging studies for clinical-high risk for psychosis to elucidate brain pathology and apply to clinical settings
小池 進介*1,2,3
*1東京大学心の多様性と適応の連携研究機構
*2東京大学大学院総合文化研究科進化認知科学研究センター
*3東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構