臨床精神医学第51巻第4号
ICD-11が気分症群の臨床に与えるインパクト
電子書籍のみ
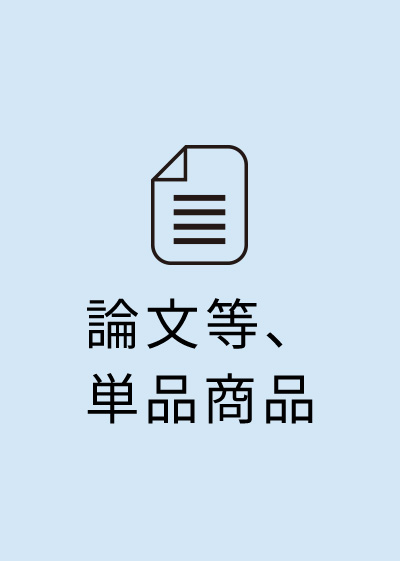
- 大森 哲郎(藍里病院あいざと精神医療研究所)
- 発行日:2022年04月28日
- 〈抄録〉
ICD-11はICD-10と比べて全体構造が大きく改変されている。ICD-10には存在した「器質性」,「症状性」,「神経症性」などの用語が消失することは,抑うつ症群の診療にも浅からぬ影響を及ぼす可能性がある。またdepressive disorderはDSM-5とほぼ同じ診断基準となり,これに対して「うつ病」の訳語が与えられる。概念に混乱もあった「うつ病」は今後これが標準となるだろう。この「うつ病」は,糖尿病や高血圧などがそうであるのと同様に,症状,成因,病態に異種性を有する幅広い状態を指し示す用語と理解すべきである。Bipolar disorderに対しては双極症の訳語が当てられる。双極性障害や双極性感情障害よりも簡潔明瞭な名称であり,訳語変更によってこの疾患の社会全般の理解が進むことが期待できる。双極症とうつ病は,もともとは躁うつ病に含まれるひとまとまりの疾患と理解されていたが,近年の研究から双極症は統合失調症との,うつ病は不安症との近縁性が示唆されている。気分症群が「双極症または関連症群」と「抑うつ症群」という下位分類に分かれたことは,その距離感を反映している。
詳細
Impact of ICD-11 on the clinical practice of mood disorders
大森 哲郎
社会医療法人あいざと会藍里病院あいざと精神医療研究所