臨床精神医学第49巻第3号
精神医学における「意識障碍」概念の全般的検討─せん妄(DSM-5)に光をあてる─
電子書籍のみ
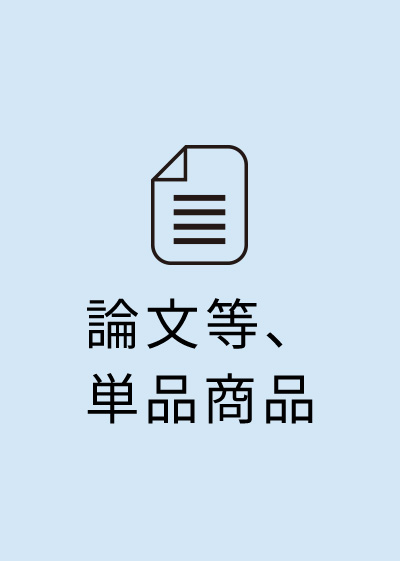
- 西依 康・他(自治医科大学)
- 発行日:2020年03月28日
- 〈抄録〉
意識障碍の研究を概観すると,(1)意識を注意や認知に関わる高次の神経機能として把握する医学生理学の視点と,(2)意識を<世界内存在>としての人間に固有な事象としてみる(広義の)現象学的精神病理学の視点を区別することができる。本論では,この二つの視点から意識障碍の諸概念を検討した。DSM-5において,せん妄(delirium)の臨床単位は「注意」と「認知」を主たるパラダイムとして構成され,「意識」のパラダイムは廃棄された。認知科学(心理学)が台頭してきて,相対的に意識の病理に関するこれまでの精神病理学研究の意義が下がっている憾みもある。意識障碍の理解が,「心不在の精神医学」(mindless psychiatry)一辺倒にならないためにも,意識障碍の精神病理学の意義は大きいと考えられる。
詳細
General considerations of pathology of consciousness in psychiatry
西依 康*1 加藤 敏*2
*1 自治医科大学精神医学講座
*2 小山富士見台病院