臨床精神医学第48巻第10号
注意欠如・多動症概念の普及は児童青年期臨床をどう変えたか
電子書籍のみ
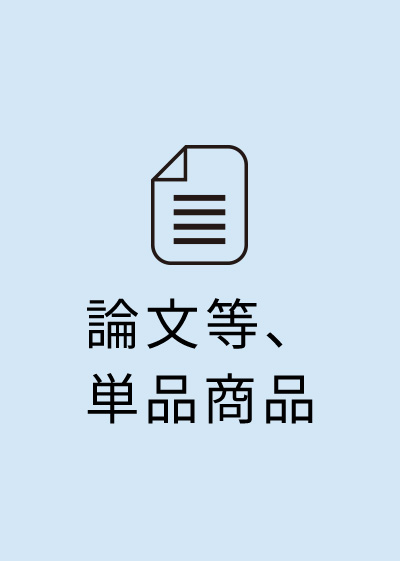
- 鈴木 太(福井大学)
- 発行日:2019年10月28日
- 〈抄録〉
注意欠如・多動症(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder; ADHD)の元になった概念が診断カテゴリとして確立したのは1950年代である。ADHDは青年になると寛解すると,かつては考えられていたが,ADHDを伴う児童の一部は成人になってもADHDの症候学的な診断基準を満たし,成人期に機能障害を伴うことが多い。児童期ADHDの治療ゴールの一つは,成人期の社会的機能の改善であり,中枢刺激薬などの抗ADHD薬は有効な治療手段である。ADHDが未治療であると,学業成績不良,反社会的行動,自動車事故,薬物の乱用,体重の増加,就労の悪化,自尊心の低下,医療や福祉サービスの利用などを生じやすい。本邦では児童期ADHDの過少診断や過少治療に関心が持たれているが,米国では過剰治療が懸念されている。構造化面接を日常臨床に導入して包括的な診断を行うなど,過少診断や過剰診断を減少させるための仕組みづくりが重要と考えられる。
詳細
How dissemination of the concept of ADHD changed the child and adolescent clinical practice
鈴木 太
福井大学子どものこころの発達研究センター