臨床精神医学第50巻第4号
歴史的観点から見たADHDの診断
電子書籍のみ
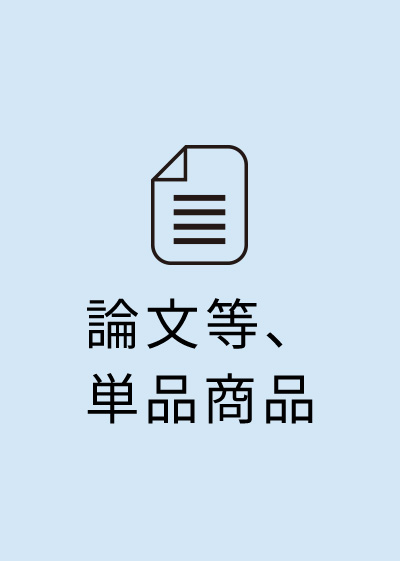
- 阿部 隆明(自治医科大学)
- 発行日:2021年04月28日
- 〈抄録〉
近代医学の成立過程にあった18世紀後半には,注意の障害に言及した文献が登場した。20世紀に入り,Stillによって「道徳的抑制の欠如」を有する行動障害の著しい小児の報告が行われた。まもなく世界的に嗜眠性脳炎が流行し,その後遺症としての多動症状が注目された。これに対し,Kramerらは脳炎と無関係のADHDに近い病態を記述した。その後,多動症状の原因として脳の微細な損傷を想定する議論を経て,最終的には症状記述的な診断名が採用され,ICD-9(1978)では小児期の多動症候群という臨床単位が登場した。ADHDという病名が初めて現れたのは,DSM-Ⅲ -R(1987)においてであり,当時は破壊的行動障害の下位分類であった。DSM-5(2013)に至って,ADHDはASDと並んで神経発達症の一つとして位置付けられた。ADHDは症状群であり,診断閾値に達しない症例も少なくないし,長ずるにしたがって症状の力点が多動から不注意へと変わることもある。現在では支援の必要性に応じて診断が与えられることになっている。
詳細
The diagnosis of ADHD from the historical viewpoint
阿部 隆明
自治医科大学とちぎ子ども医療センター子どもの心の診療科